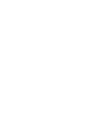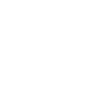+86-13380107575
+86-13380107575 +86-13380107575
+86-13380107575検出ピンは機械標準部品中の検出治具シリーズ製品であり、ピン類部品に応用される比較的特殊な製品でもある。一般的には単頭検出ピン、二頭検出ピン、ばね検出ピンなどに簡単に分けることができ、いくつかの検出ピンの違いは単頭検出か二頭検出かにあることが明らかになった。
1.検出ピンの構成
検出ピンの基本構造は、ガイド部、検出部、ハンドル部の3つの部分から構成されています。検査ピンを使用する過程で、検査ピンが検査作用をよりよく実現することを保障すると同時に、検査効果をさらに正確にするために、一般的に検査ピンをガイドブッシュに取り付ける。具体的な方法は、適切なサイズのガイドブッシュと検出ピンの検出部位を接続することで、検出ピンの位置決め効果をより正確にすることができます。
2.検出ピンの具体的な役割
検出治具の1つとして、検出ピンのも主要な役割は、検出孔のサイズと具体的な位置度の検出を実現することである。また、検出ピンの検出作用もその自体の構造と検出すべき穴の形状との関係に依存しており、一般的にはこの2つの部分の違いに基づいて検出ピンを回転構造と回転構造だけでなく回転構造に分けることができる。
3.検出ピンの使用上の注意
1)検出ピンを使用して検出穴を検出する場合、部品に直径と公差の要求が同じ穴が複数ある場合、検出ピンの数と検出穴の数が同じである必要はありません。一般的には、検出ピンを1つ使用するだけで、すべての検出される穴の検出タスクを完了することができます。
2)もし検出すべき穴が金型を用いて部品表面に一括加工したものであれば、も良い検出方法は検出ピンを用いて頭尾間の間隔がも大きい2つの検出すべき穴を検出することであり、中間の穴については無視することができ、必ずしも各穴に対して検出ステップを完成する必要はない。
3)検査ピンの取り付け固定の過程で、一般的にワイヤーロープを固定工具として使用し、検査ピンを検査対象部品の適切な位置に固定する。
4)検査対象部品に使用する検査ピンが3個を超えている場合、よりよく区別するために、検査対象部品に具体的な数字をマークして異なる検査ピンに対応する必要がある。